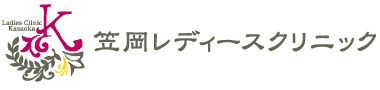■時期:7月7日~7月20日

小暑(しょうしょ)は、通常7月7日頃から始まる、夏の始まりを示す節気です。
夏の本格的な暑さの始まりを意味し、梅雨が明ける時期でもあります。
暑さが本格化する時期でもあるので、熱中症対策や涼しく過ごすための工夫も必要になります。
この時期の旬の食べ物
とうもろこし
甘みが強く、シャキッとした食感が楽しめる夏の代表的な野菜。焼く、茹でる、蒸すなどの調理方法が一般的です。
・炭水化物が豊富で、エネルギー源として優秀
・食物繊維が腸内環境を整え、便秘予防に役立つ
・カリウムが塩分の排出を助け、高血圧予防に効果的
・ビタミンB1・B2が糖質や脂質の代謝を助け、疲労回復に貢献
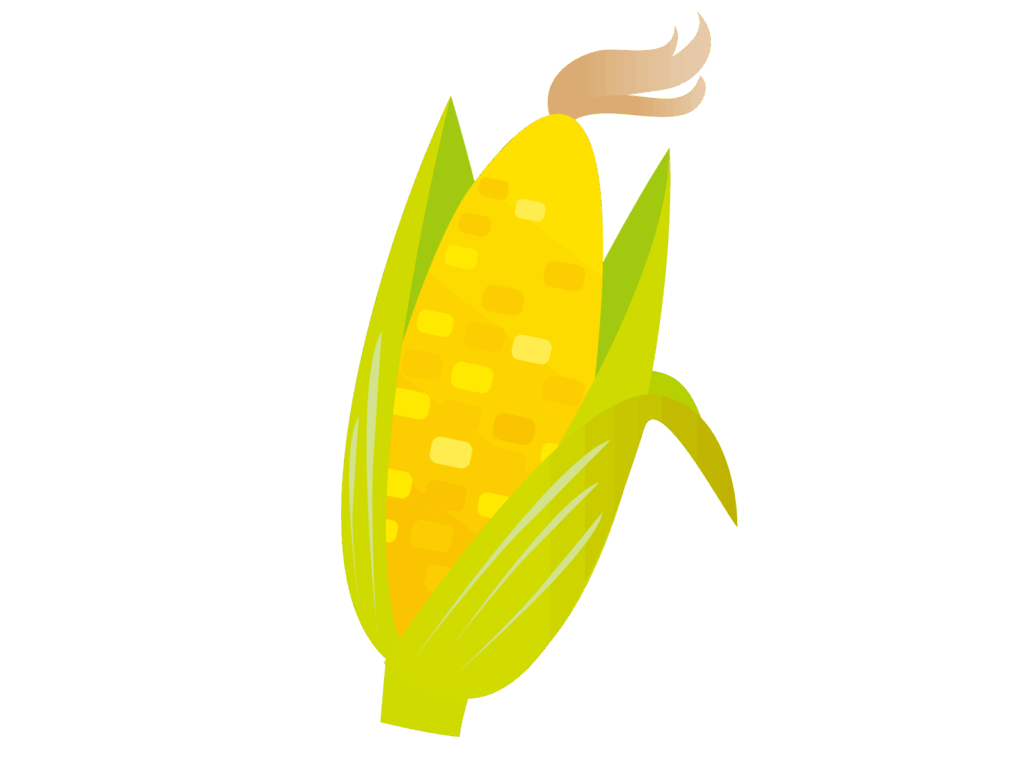
枝豆
大豆の未熟な状態で収穫されるため、豆類と野菜の栄養を兼ね備えています。塩茹でして食べるのが一般的で、おつまみとしても人気。
・タンパク質が豊富で、「畑の肉」とも呼ばれる
・ビタミンB1が糖質の代謝を助け、スタミナ不足を解消
・メチオニンがアルコールの分解を促し、肝機能をサポート
・カリウムがむくみ解消や高血圧予防に役立つ
・鉄分が多く、貧血予防にも効果的

スイカ
スイカはウリ科の果物で、約90%が水分で構成されているため、夏の水分補給に最適です。甘くてみずみずしい果肉が特徴で、赤色の果肉はリコピンを豊富に含んでいます。
また、スイカの皮や種にも栄養が含まれており、皮は漬物や炒め物に、種はローストして食べることができます。スイカは栄養を余すことなく楽しむことができます。
・ビタミンC:抗酸化作用があり、肌の健康維持に役立つ
・カリウム:体内の水分バランスを整え、むくみの予防に効果的
・シトルリン:血流を改善し、疲労回復をサポート
・β-カロテン:体内でビタミンAに変換され、視力や皮膚の健康を維持
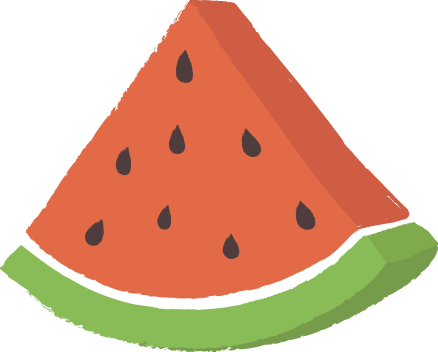
熱中症について
熱中症の症状
初期症状
・めまい
・立ちくらみ
・大量の発汗
・筋肉痛
・生あくび
症状が進むと
・頭痛
・吐き気
・倦怠感
・虚脱感
主な応急処置
症状が軽いうちに適切な対応をすることで、重症化を防ぐことができます。
1. 涼しい場所へ移動
・エアコンの効いた室内や風通しの良い日陰へ移動する。
・可能なら扇風機やうちわで風を送る。
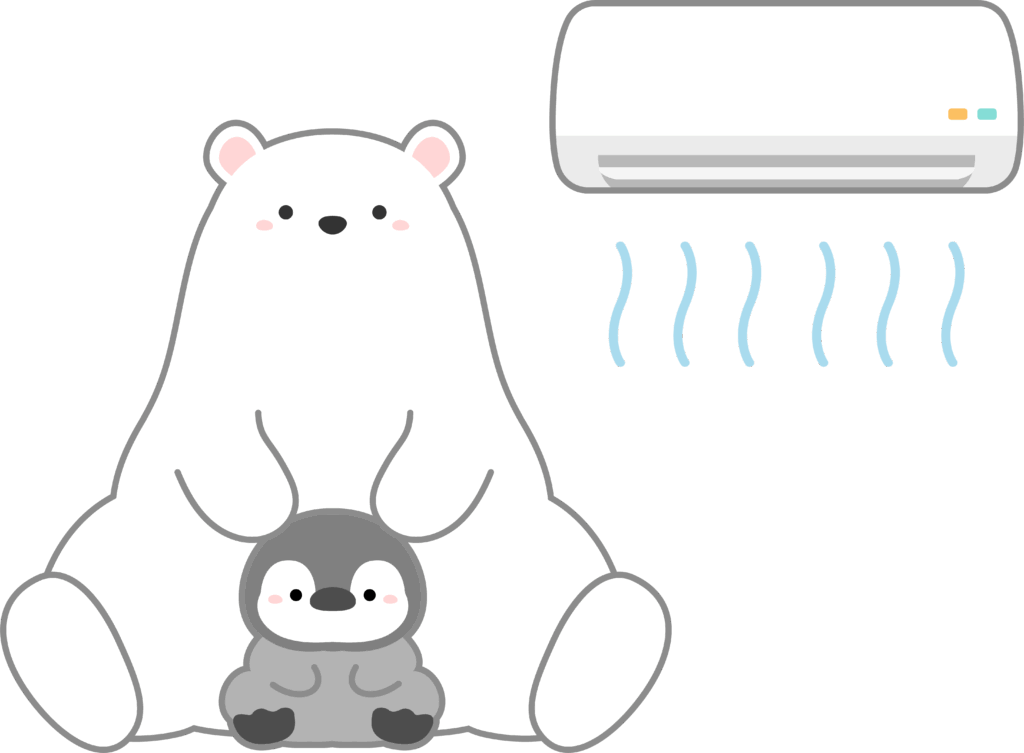
2. 体を冷やす
・首、脇の下、太ももの付け根を冷却する(氷や冷却シートを使用)。
・服をゆるめ、皮膚に水をかけて扇ぐことで体温を下げる。
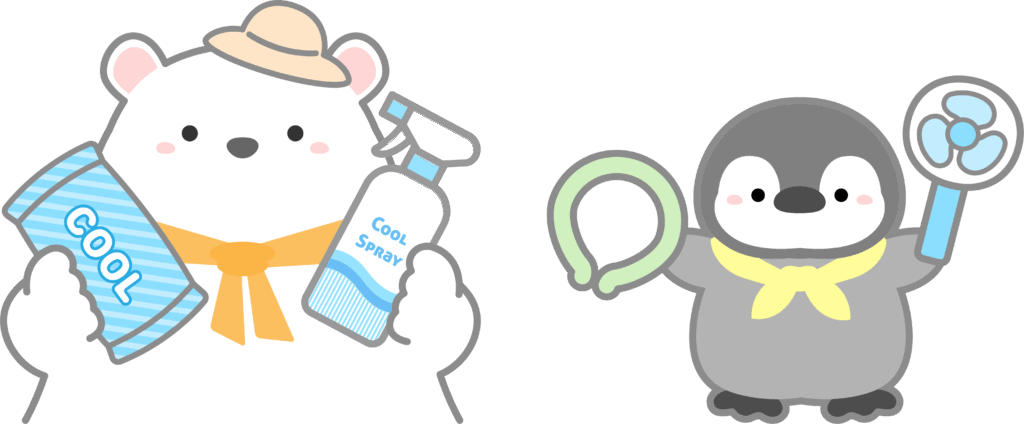
3. 水分・塩分補給
・経口補水液やスポーツドリンクを飲む(ただし、意識がある場合のみ)。
・水だけでなく、塩分も補給するために梅干しや塩飴を活用する。

4. 症状が改善しない場合は医療機関へ
・意識がもうろうとしている、水分補給ができない場合はすぐに救急車を呼ぶ。
・応急処置をしながら、医療機関へ搬送する。

1.塩分・ミネラル補給
・汗とともに失われる塩分やミネラルを補うため、梅干し・塩飴・スポーツドリンクなどを活用。
・カリウムを含むバナナやトマトもおすすめです!

2.涼しい環境を作る
・エアコンや扇風機を適切に使い、室温を調整。
・すだれや遮光カーテンで直射日光を防ぐ。
・打ち水をすると、気化熱で周囲の温度が下がる。
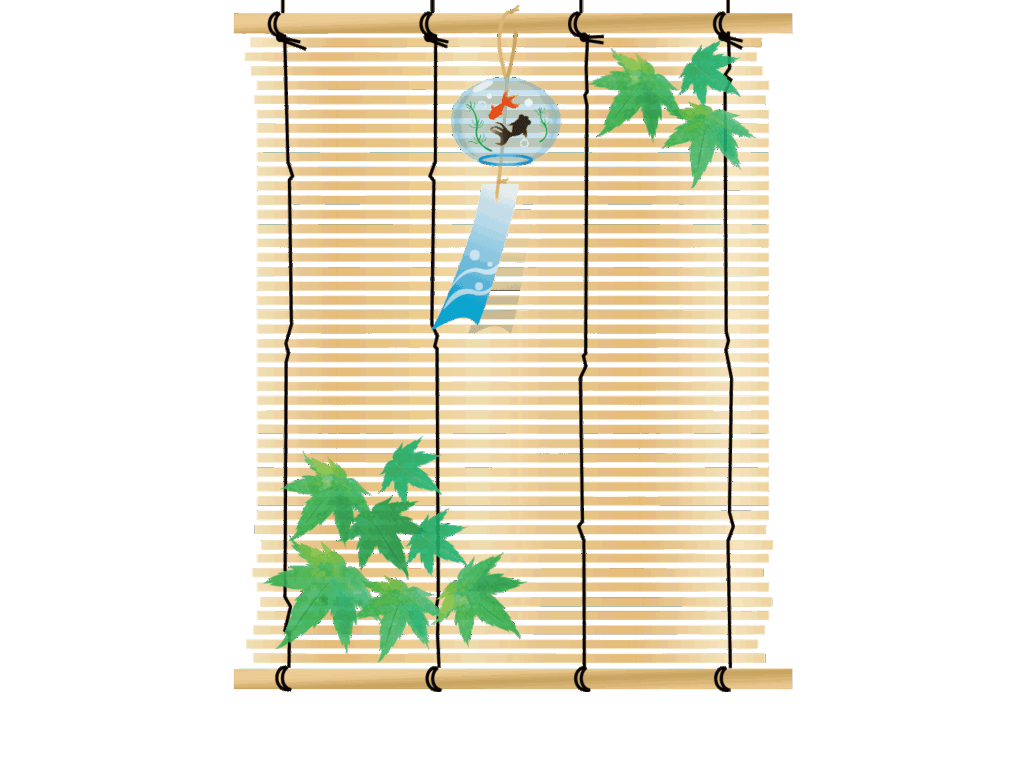
3.服装などの工夫
・通気性の良い素材(麻・綿)を選ぶ。
・ゆったりとした服で風通しを良くする。
・帽子や日傘を使い、直射日光を避ける。
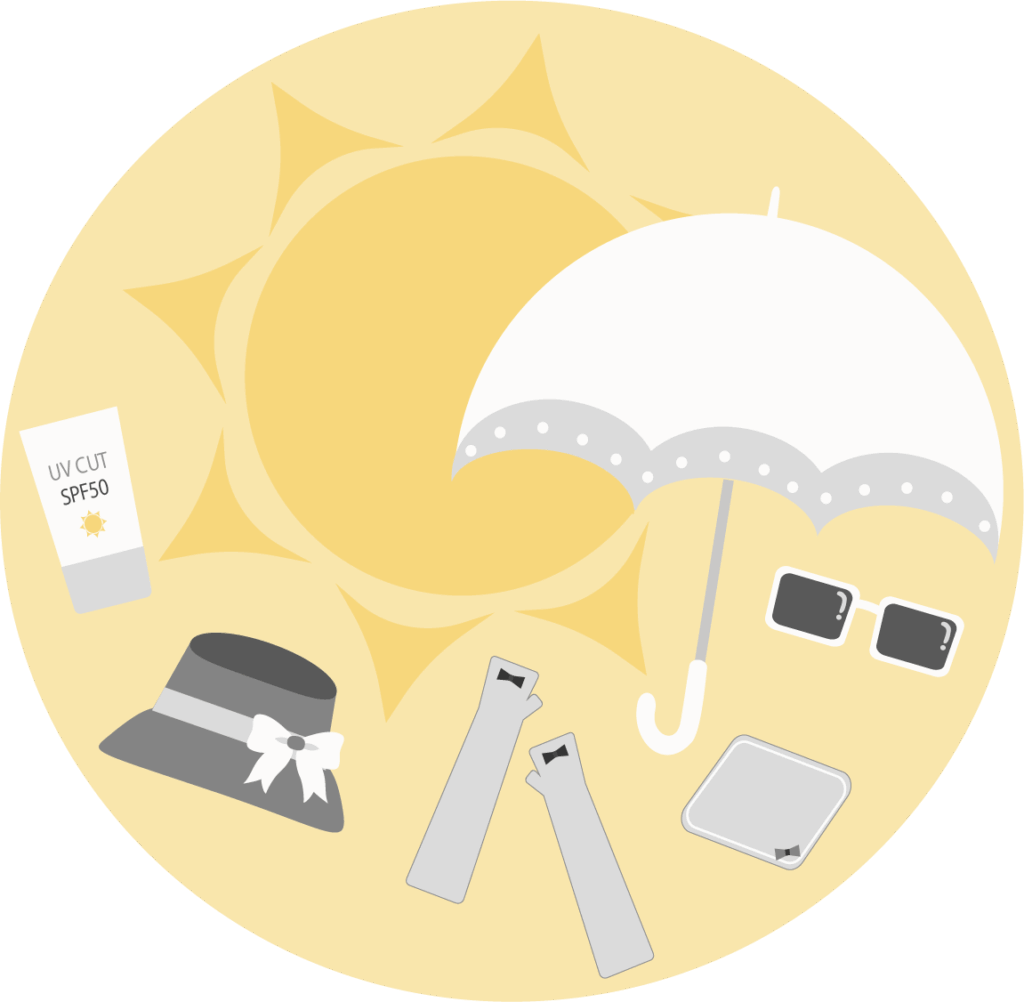
4.適度な休憩を取る
・長時間の屋外活動は避け、こまめに休憩を取る。
・日陰や涼しい場所で体を休める。
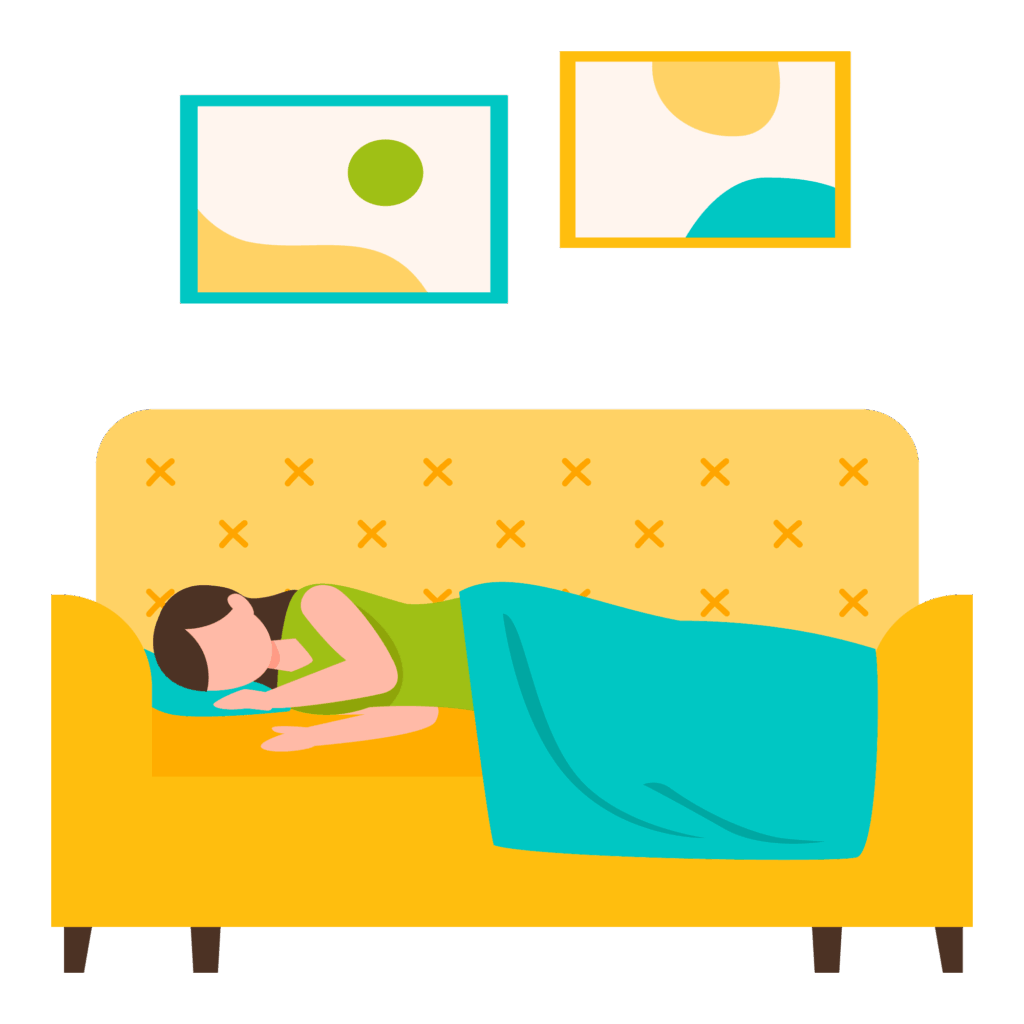
5.食事で体を整える
・夏野菜(きゅうり・ゴーヤなど)で体を冷やす。
・ビタミンB1を含む豚肉で疲労回復。
・水分の多い食材(スイカ・豆腐など)を積極的に摂る。
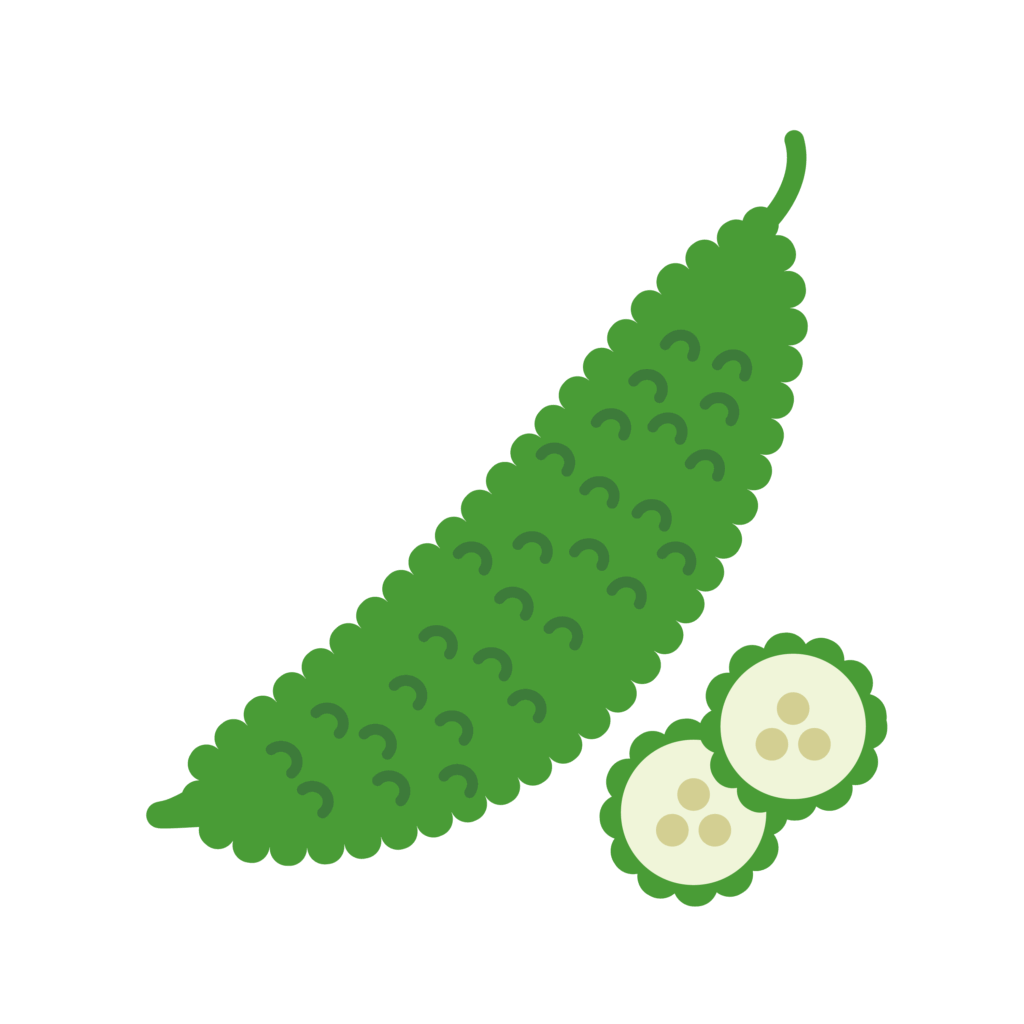
熱中症は早めの対応が重要です!
特に、高齢者や子どもは症状が急激に悪化することがあるので、注意が必要です。
詳しく知りたい方は、厚生労働省の公式情報をご覧ください。
熱中症予防のための情報・資料サイト